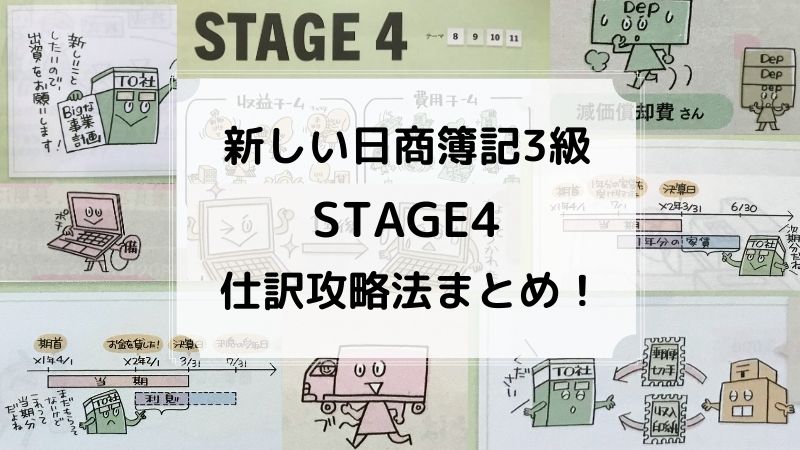2020年4月1日に出版された『Let’s Start! 新しい日商簿記3級 テキスト&問題集 2020年度版』(「新しい日商簿記3級」)は、とにかく画期的な簿記本です。
テキストは全ページオールカラーで、ページレイアウトのセンスや色使いがvery good!
最高に美しく読みやすい簿記テキストに仕上がっています。
キャラ化した勘定科目や簡単な場面設定により、とっつきにくい簿記が楽しく学べるので、これから簿記の勉強を始めてみようかな…と思っている方におすすめです。
簿記の基本は仕訳です。
「仕訳を制する者は簿記を制す!」と言われるほど重要なので、検定試験の合格を目指すなら、仕訳は何としても得意にしておきたいところ。
このページでは、「新しい日商簿記3級」STAGE4に登場する仕訳の徹底攻略法をまとめました。
▼STAGE2とSTAGE3、STAGE7はこちら。
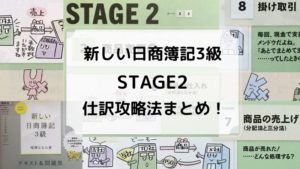 【新しい日商簿記3級テキスト STAGE2】一発で覚えられる!簿記3級の仕訳攻略法まとめ
【新しい日商簿記3級テキスト STAGE2】一発で覚えられる!簿記3級の仕訳攻略法まとめ
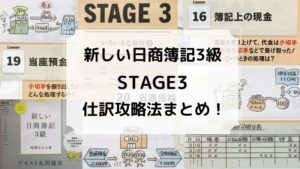 【新しい日商簿記3級テキスト STAGE3】簿記3級の仕訳攻略法まとめ。現金と預金、立替金と給料の支払いなど
【新しい日商簿記3級テキスト STAGE3】簿記3級の仕訳攻略法まとめ。現金と預金、立替金と給料の支払いなど
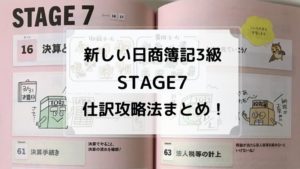 【新しい日商簿記3級テキスト STAGE7】仕訳攻略法まとめ。売上原価の算定(しくりくりし)、法人税等の計上など
【新しい日商簿記3級テキスト STAGE7】仕訳攻略法まとめ。売上原価の算定(しくりくりし)、法人税等の計上など
STAGE4のテーマは以下のとおりです。
- 貸倒れと貸倒引当金
- 有形固定資産と減価償却
- 株式の発行
- 消耗品
- 通信費と租税公課
- 収益・費用の未収・未払い
- 収益・費用の前受け・前払い
この「新しい日商簿記3級」STAGE4に登場する仕訳の中から特に重要な問題を厳選して
- 問題文
- 解答(仕訳)
- この仕訳になる理由
の順で掲載しました。
※仕訳問題は、滝澤 ななみ 先生の許可を得て掲載しています。「この仕訳になる理由」は、当サイトで作成したものです。
問題文の下をクリックすると窓が開いて、解答(仕訳)とこの仕訳になる理由が読めるようになっています。
問題文を読んで、どんな仕訳になるのか少し考えてみる➡クリックして解答(仕訳)& この仕訳になる理由を見て答え合わせ……という感じで、テキストを参照しながら使ってみてください。
もし解けない問題があったり、疑問点が生じた場合は、必ず「新しい日商簿記3級」に戻って確認しながら進めてくださいね。
それでは、合格目指してがんばっていきましょう!
新しい日商簿記3級 STAGE4の仕訳
貸倒れと貸倒引当金の仕訳
貸倒れとは、得意先の倒産などにより、その得意先に対する売掛金や受取手形などの債権を回収できなくなることをいいます。
この貸倒れに備えて、決算日において売掛金や受取手形の残高があるときは、将来貸倒れがおこる可能性を見積もって、貸倒引当金を設定します。
決算日における貸倒引当金の設定
貸倒引当金の設定額:100円×2%=2円
(貸) 貸倒引当金 2
●「貸倒引当金」(負債)が増加した➡「貸倒引当金」は貸方(右側)
決算日における貸倒引当金の設定(前期の貸倒引当金が残っているとき)
①貸倒引当金の設定額:300円×2%=6円
②追加で計上する額:6円-2円=4円
(貸) 貸倒引当金 4
●「貸倒引当金」(負債)が増加した➡「貸倒引当金」は貸方(右側)
貸倒れの処理
実際に得意先が倒産し、売掛金が回収できなくなったときの仕訳です。
前期発生の売掛金が貸し倒れた場合と、当期発生の売掛金が貸し倒れた場合で処理方法が異なります。
前期発生の売掛金が貸し倒れたとき
貸倒引当金を超える額:50円-2円=48円
(借) 貸倒損失 48
(貸) 売掛金 50
●「貸倒損失」(費用)が増加した➡「貸倒損失」は借方(左側)
●「売掛金」(資産)が減少した➡「売掛金」は貸方(右側)
当期発生の売掛金が貸し倒れたとき
(貸) 売掛金 50
●「売掛金」(資産)が減少した➡「売掛金」は貸方(右側)
償却債権取立益
前期(以前)に貸倒れ処理した売掛金等を、当期に回収できたときは、償却債権取立益で処理します。
前期に貸倒れ処理した売掛金等を回収したとき
(貸) 償却債権取立益 10
●「償却債権取立益」(収益)が増加した➡「償却債権取立益」は貸方(右側)
有形固定資産の購入、付随費用の仕訳
有形固定資産を購入したときは、購入したときの本体価格(購入代価)に、使うまでにかかった費用(付随費用)を含めた金額(取得原価)で仕訳します。
有形固定資産を購入したとき
取得原価:780円+20円=800円
(貸) 当座預金 800
●「当座預金」(資産)が減少した➡「当座預金」は貸方(右側)
取得原価:300円+10円=310円
(貸) 当座預金 300
(貸) 現 金 10
●「当座預金」(資産)が減少した➡「当座預金」は貸方(右側)
●「現金」(資産)が減少した➡「現金」は貸方(右側)
減価償却の仕訳
減価償却費は
減価償却費=(取得原価-残存価額)÷耐用年数
で求めます。
減価償却費の計算
減価償却費:(400円-40円)÷4年=90円
または
減価償却費:400円×0.9÷4年=90円
減価償却費の記帳方法
減価償却費:400円×0.9÷4年=90円
(貸) 備品減価償却累計額 90
●「備品減価償却累計額」(資産のマイナス)が増加した➡「備品減価償却累計額」は貸方(右側)
期中に取得しているとき
1年分の減価償却費:(480円-0円)÷4年=120円
当期分の減価償却費:120円÷12か月×8か月=80円
(貸) 備品減価償却累計額 80
●「備品減価償却累計額」(資産のマイナス)が増加した➡「備品減価償却累計額」は貸方(右側)
有形固定資産の売却の仕訳
有形固定資産を売却したときの仕訳です。
まず、期首に有形固定資産を売却した場合、次に、期末に有形固定資産を売却した場合、最後に期中に有形固定資産を売却した場合を考えます。
期首に有形固定資産を売却したとき
(借) 備品減価償却累計額 90
(貸) 備 品 360
(貸) 固定資産売却益 30
●「備品減価償却累計額」(資産のマイナス)が減少した➡「備品減価償却累計額」は借方(左側)
●「備品」(資産)が減少した➡「備品」は貸方(右側)
●「固定資産売却益」(収益)が増加した➡「固定資産売却益」は貸方(右側)
(借) 備品減価償却累計額 90
(借) 固定資産売却損 20
(貸) 備 品 360
●「備品減価償却累計額」(資産のマイナス)が減少した➡「備品減価償却累計額」は借方(左側)
●「固定資産売却損」(費用)が増加した➡「固定資産売却損」は借方(左側)
●「備品」(資産)が減少した➡「資産」は貸方(右側)
期末に有形固定資産を売却したとき
なお、当期分の減価償却費も定額法(残存価額は0円、耐用年数は4年)により計上すること
当期分の減価償却費:(360円-0円)÷4年=90円
(借) 備品減価償却累計額 90
(借) 減価償却費 90
(貸) 備 品 360
(貸) 固定資産売却益 20
●「備品減価償却累計額」(資産のマイナス)が減少した➡「備品減価償却累計額」は借方(左側)
●「減価償却費」(費用)が増加した➡「減価償却費」は借方(左側)
●「備品」(資産)が減少した➡「資産」は貸方(右側)
●「固定資産売却益」(収益)が増加した➡「固定資産売却益」は貸方(右側)
期中に有形固定資産を売却したとき
なお、当期は✖3年4月1日から✖4年3月31日までの1年で、当期分の減価償却費も定額法(残存価額は0円、耐用年数は4年)により月割りで計上すること。
1年分の減価償却費:(360円-0円)÷4年=90円
当期分の減価償却費:90円÷12か月×4か月=30円
(借) 備品減価償却累計額 90
(借) 減価償却費 30
(借) 固定資産売却損 40
(貸) 備 品 360
●「備品減価償却累計額」(資産のマイナス)が減少した➡「備品減価償却累計額」は借方(左側)
●「減価償却費」(費用)が増加した➡「減価償却費」は借方(左側)
●「固定資産売却損」(費用)が増加した➡「固定資産売却損」は借方(左側)
●「備品」(資産)が減少した➡「備品」は貸方(右側)
未払金と未収入金の仕訳
有形固定資産や消耗品など、商品以外のものを後払いで購入したときの、あとで代金を支払わなければならない義務は未払金(負債)で処理します。
有形固定資産など、商品以外のものを売却し、代金はあとで受け取るとしたときの、あとで代金を受け取る権利は未収入金(資産)で処理します。
有形固定資産等を後払いで購入したとき
(貸) 未払金 500
●「未払金」(負債)が増加した➡「未払金」は貸方(右側)
(貸) 未払金 100
●「未払金」(負債)が増加した➡「未払金」は貸方(右側)
有形固定資産等を売却代金をあとで受け取るとき
(借) 車両運搬具減価償却累計額 300
(借) 固定資産売却損 50
(貸) 車両運搬具 500
●「車両運搬具減価償却累計額」(資産のマイナス)が減少した➡「車両運搬具減価償却累計額」は借方(左側)
●「固定資産売却損」(費用)が増加した➡「固定資産売却損」は借方(左側)
●「車両運搬具」(資産)が減少した➡「車両運搬具」は貸方(右側)
有形固定資産の貸借の仕訳
家賃を支払ったとき
敷金(差入保証金):100円×2か月=200円
(借) 差入保証金 200
(貸) 現 金 300
●「差入保証金」(資産)が増加した➡「差入保証金」は借方(左側)
●「現金」(資産)が減少した➡「現金」は貸方(右側)
株式会社の設立の仕訳
株式を発行したとき(設立時)
資本金:@50円×100株=5000円
(貸) 資本金 5,000
●「資本金」(資本)が増加した➡「資本金」は貸方(右側)
増資の仕訳
増資をしたとき
資本金:@60円×50株=3,000円
(貸) 資本金 3,000
●「資本金」(資本)が増加した➡「資本金」は貸方(右側)
消耗品の仕訳
消耗品を購入したとき
(貸) 現 金 100
●「現金」(資産)が減少した➡「現金」は貸方(右側)
通信費と租税公課の仕訳
切手やはがき、収入印紙を購入したとき
(借) 租税公課 200
(貸) 現 金 300
●「租税公課」(費用)が増加した➡「租税公課」は借方(左側)
●「現金」(資産)が減少した➡「現金」は貸方(右側)
決算日に切手やはがき、印紙が残っているとき
通信費(費用)として費用計上した郵便切手やはがき、租税公課(費用)として費用計上した収入印紙が、決算日において残っている場合には、残っている分を通信費(費用)や租税公課(費用)から貯蔵品(資産)に振り替えます。
(貸) 通信費 20
(貸) 租税公課 30
●「通信費」(費用)が減少した➡「通信費」は貸方(右側)
●「租税公課」(費用)が減少した➡「租税公課」は貸方(右側)
翌期首の処理
決算日において、通信費(費用)や租税公課(費用)から貯蔵品(資産)に振り替えたときは、翌期首に決算時の仕訳の逆仕訳(再振替仕訳)をしてもとの勘定に振り戻します。
(借) 貯蔵品 50
(貸) 通信費 20
(貸) 租税公課 30
(借) 租税公課 30
(貸) 貯蔵品 50
●「租税公課」(費用)が増加した➡「租税公課」は借方(左側)
●「貯蔵品」(資産)が減少した➡「貯蔵品」は貸方(右側)
収益・費用の未収・未払いの仕訳
収益の未収
本日(3月31日)、決算日につき、受取利息の未収計上を行う。
当期分の利息:600円×2%÷12か月×2か月=2円
(貸) 受取利息 2
●「受取利息」(収益)が増加した➡「受取利息」は貸方(右側)
翌期首の仕訳
↓
当期の2月1日にA社に対して現金600円(年利率2%、貸付期間6か月、返済日に利息を受け取る)を貸し付けた。
本日(3月31日)、決算日につき、受取利息の未収計上を行う。
当期分の利息:600円×2%÷12か月×2か月=2円
(貸) 未収利息 2
●「未収利息」(資産)が減少した➡「未収利息」は貸方(右側)
費用の未払い
(貸) 未払利息 2
●「未払利息」(負債)が増加した➡「未払利息」は貸方(右側)
翌期首の仕訳
↓
当期分の利息の未払額が2円ある。
(貸) 支払利息 2
●「支払利息」(費用)が減少した➡「支払利息」は貸方(右側)
収益・費用の前受け・前払いの仕訳
収益の前受け
本日(3月31日)、決算日につき、家賃の前受処理を行う。
次期分の家賃:1,200円÷12か月×3か月=300円
(貸) 前受家賃 300
●「前受家賃」(負債)が増加した➡「前受家賃」は貸方(右側)
翌期首の仕訳
↓
当期の7月1日にB社に対して建物を貸し付け、1年分の家賃1,200円を受けとった。
本日(3月31日)、決算日につき、家賃の前受処理を行う。
次期分の家賃:1,200円÷12か月×3か月=300円
(貸) 受取家賃 300
●「受取家賃」(収益)が増加した➡「受取家賃」は貸方(右側)
費用の前払い
(貸) 支払家賃 300
●「支払家賃」(費用)が減少した➡「支払家賃」は貸方(右側)
翌期首の仕訳
↓
家賃の前払い額が300円ある。
(貸) 前払家賃 300
●「前払家賃」(資産)が減少した➡「前払家賃」は貸方(右側)
訂正仕訳(修正仕訳)
訂正仕訳(修正仕訳)
① 誤った仕訳
(借) 現 金 2,000
(貸) 売掛金 2,000
② ①の逆仕訳
(借) 売掛金 2,000
(貸) 現 金 2,000
③ 正しい仕訳
(借) 現 金 200
(貸) 売掛金 200
②誤った仕訳の逆仕訳と③正しい仕訳を合わせたものが解答の仕訳(訂正仕訳)となります。
(貸) 現 金 1,800
●「現金」(資産)が減少した➡「現金」は貸方(右側)
まとめ
以上、「新しい日商簿記3級」STAGE4に登場する仕訳を見てきました。
▼STAGE2とSTAGE3、STAGE7はこちら。
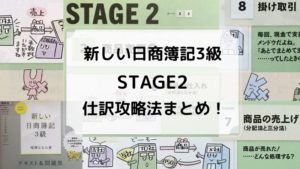 【新しい日商簿記3級テキスト STAGE2】一発で覚えられる!簿記3級の仕訳攻略法まとめ
【新しい日商簿記3級テキスト STAGE2】一発で覚えられる!簿記3級の仕訳攻略法まとめ
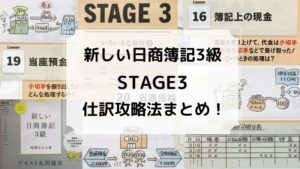 【新しい日商簿記3級テキスト STAGE3】簿記3級の仕訳攻略法まとめ。現金と預金、立替金と給料の支払いなど
【新しい日商簿記3級テキスト STAGE3】簿記3級の仕訳攻略法まとめ。現金と預金、立替金と給料の支払いなど
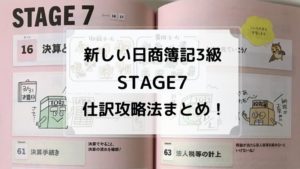 【新しい日商簿記3級テキスト STAGE7】仕訳攻略法まとめ。売上原価の算定(しくりくりし)、法人税等の計上など
【新しい日商簿記3級テキスト STAGE7】仕訳攻略法まとめ。売上原価の算定(しくりくりし)、法人税等の計上など
STAGE4は、「貸倒れと貸倒引当金、貸倒れの処理、償却債権取立益、有形固定資産の購入・付随費用、減価償却、有形固定資産の売却、未払金と未収入金、有形固定資産の貸借、株式会社の設立、増資、消耗品、通信費と租税公課、収益・費用の未収・未払い、収益・費用の前受け・前払い、訂正仕訳」などのテーマが詰まった盛りだくさんの内容でした(一部取り上げていないテーマがあります)。
いずれも試験頻出のテーマで、簿記を勉強していく上では、必ず理解しておかなくてはならない項目ばかり。知識を使いこなせるようになるまで、しっかり勉強しておきましょう。
仕訳の作り方
- その勘定科目が資産・負債・収益・費用・純資産のどれにあたるのか
- 資産・負債・収益・費用・純資産のホームポジションは、借方(左側)・貸方(右側)のどちらか➡資産と費用は借方(左側)、負債と収益と純資産は貸方(右側)
の2つが、仕訳を作るためには必須の知識となります。
もし仕訳の作り方を忘れたら、この2つのポイントに立ち返ってもう一度考えてみてください。
「新しい日商簿記3級」STAGE1のLesson3「仕訳の作り方」には、簿記の一番重要なポイントがよくまとめられています。勉強し始めの時期は、ここを何度も繰り返し読んで「仕訳の作り方」をマスターしてくださいね!